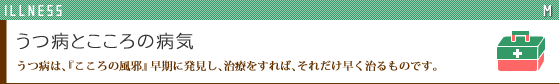 |
| |
 |
 |
 |
 うつ病は『心の肺炎』 うつ病は『心の肺炎』
 うつ病の特徴的な9つの症状 うつ病の特徴的な9つの症状
 うつ病に特徴的な"症状の波" うつ病に特徴的な"症状の波"
 うつ病でみられるこころの3症状 うつ病でみられるこころの3症状
 うつ病でみられるからだの症状 うつ病でみられるからだの症状
 「仮面うつ病」とは 「仮面うつ病」とは
 うつ病における睡眠障害 うつ病における睡眠障害
|
 |
 |
| うつ病は『心の肺炎』 |
 |
|
 |
うつ病は“心の風邪”ともいわれます。誰でも経験しうる病気なのでそう呼ばれるのですが、その比喩の軽さとは裏腹に、うつ病は心身ともに非常につらい状態です。“心の風邪”というよりも、緊急性がともなう分、“心の肺炎”という方が適切かもしれません。
|
| ◆うつ病とは何か? |
うつ病は、ギリシャ時代に存在が確認されている病気ですが、価値観の多様化やテクノロジーの進展、人間関係の希薄化などのために非常にストレスの強い生活にさらされている現代では、ますますその温床を広げています。
実際、うつ病をはじめとする精神疾患の方は増えており、人々への「生活の質を下げる」という点では健康上の脅威になっています。また、近年、うつ病と自殺の関係が注目され、大きな社会問題にまで発展しています。うつ病の予防や早期発見・早期治療が可能な社会体制づくりが急務になっているのです。
うつ病にかからないまでも、気分の落ち込み程度は、誰もが日常的に体験するものです。つらいこと、嫌なことがあれば暗い気持ちになりますし、身内の死などのショッキングな出来事を経験すれば、深い悲しみと気分の落ち込みに襲われても当然です。それはネガティブな状況に対するごく当たり前の“心の反応”です。
ただし、そのように一時的な“うつ”の状態に陥ることがあっても、誰もがそのまま治療の必要な“うつ病”に陥るわけではありません。しかし、一時的なうつ状態から、治療が必要なうつ病に移行してしまう人も、確実に存在するのです。
では、一時的なうつとうつ病とは、いったいどこが違うのでしょうか?
|
| ◆一時的な「うつ」と「うつ病」 |
基本的に“軽度のうつ”と「うつ病」の間に明確な線引きをすることはできません。
もともと“うつ”とは、仕事に対してやる気がなくなったり、それまで大好きだったものにさえ喜びを感じられなくなったりという、いわゆる“気分が落ち込んだ”状態のことを指します。
このような気分の落ち込みは、健康な人でも日常的に何度も経験しますが、たいていの場合、「クヨクヨしてもしょうがない」と気持ちを切り替えたり、「次はこうしよう!」と割り切ったりして、次の行動に進んでいけるものです。
ところが、そうした気持ちの切り替えや割り切りができなくなり、気持ちが落ち込んだままになってしまうことがあります。“うつ病”の専門家の助けが必要とされるのは、そんな場合なのです。
つまり、“うつ病”とは「自力で対処できなくなり、治療を必要としている状態」を指し、誰もが感じる“うつ”に「治療が必要である」という意味で“病”という文字がついているのだと考えてください。
しかし、「病」がついているからといって“うつ”を“異常”ととらえるのではなく、むしろ「医学的な治療で改善することができる」状態だとみなすことが大切です。
なお、“うつ病”や“うつ”のほかに“うつ状態”“抑うつ状態”などの表現が使われることもありますが、意味的にはどれもほとんど変わりはなく、基本的に「精神的なエネルギーが低下した状態」を指しています。
|
| ◆うつ病は「こころの風邪」か? |
先にも述べたように、うつ病は「心の風邪」にたとえられることがよくあります。誰でもかかりうる病気であるという意味では、確かにうつ病は風邪に似ています。
しかしその一方で、うつ病は非常に強い苦痛をともない、通常の生活が送れなくなるなど、生活の質が著しく低下する場合があります。そして、そこから逃れたいと、死の願望を抱くことすらあるのです。その意味では風邪よりも肺炎といえます。
さらに、うつ病になると、「自分はダメな人間だ」などと一人で思い悩み、苦しくても外に助けを求められなくなったり、自分が病気であること自体を認められなくなったり…と、雪だるま式にどんどんうつが深まり、自力で回復することが不可能な状態に至ります。
うつ病を「心の風邪」と軽くとらえ、放っておいても治ると考えるのは禁物です。うつうつとした気分になることは誰でもあります。しかし、ただの落ち込んだ気分と、そこから自力で抜け出せなくなっている状態とを見分けるためにも、うつ病に関して正しい知識をもつことが必要です。
|
| ◆“うつ病”は回復力が衰えた状態 |
次に、“うつ病”とはどういう状態なのか、どうして気持ちの切り替えができなくなってしまうのかを、人間の心のはたらきから考えてみましょう。
うきうきしたり、落ち込んだりといった気分の変動は、誰でも日常的に経験するものです。また、人間が何かを見たり聞いたりしたときに、自然と心が動かされ、知・情・意――すなわち、知性や感情、意欲などがはたらいて、「美しい/醜い」「感じがいい/悪い」といった価値判断を行ってしまうのも、ごく自然な反応でしょう。
このように、外部からの刺激に対する反応を、経験として積み重ねることによって、人の「心」は柔軟な弾力性を獲得していきます。
嫌なことが続いたり、非常にショックなことがあったりすると、人の「気分」は落ち込みます。しかし、落ち込んだり、めいったりしても、柔軟な心にはその落ち込みをはね返し、徐々に気分を上向きに切り替えていけるような回復力が備わっています。それは傷を負ったり、風邪をひいたりしたときに、とくに“治療”をしなくても、自然に治っていくことにも似ています。
ところが“うつ病”に陥った人の心は、回復力が極度に衰えてしまっているのです。からだの病気でも、回復力が衰えている状態では、せっかくの栄養のある食物を摂っても、その食物を消化して取り込むことができず、むしろ無理がたたって吐いてしまうなど、かえって症状を悪化させてしまう場合があります。うつ病の場合も同様で、気分の落ち込みがあまりに強くなると、がむしゃらに立ち直ろうとしてもうまくいかず、逆に立ち直ろうとすることによって、うつが深まってしまうことになります。
そうなると、もはや自力で気持ちを切り替えたり、割り切ったりすることは難しくなるばかりか、どんどん悪い方向に傾いて、ついには死にたい気分すらつのってくるのです。そうした状態が長引けば、ふだんの生活を維持することも難しくなってしまいます。
うつ病を「心の風邪」ととらえると、軽く考えてしまい、治療が後手に回ることさえあります。うつ病は「心の肺炎」なのです。軽く考えて放っておかず、早期に対処しましょう。 |
 |
|