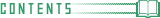 |
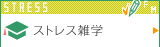 |
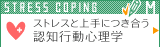 |
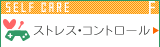 |
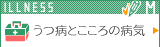 |
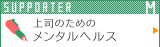 |
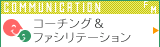 |
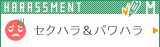 |
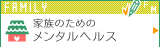 |
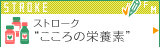 |
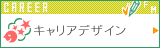 |
 |
 |
・・・ フリー |
 |
・・・ 一部メンバー限定 |
 |
・・・ メンバー限定 |
 |
・・・ チェックもの有 |
 |
|
|
|
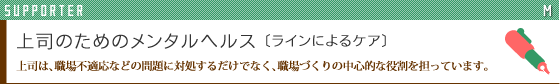 |
| |
 |
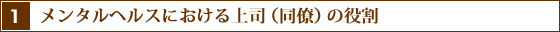 |
 |
 上司のためのストレスの基礎知識 上司のためのストレスの基礎知識  SOSに気づくのは誰? SOSに気づくのは誰?  上司に期待すること 上司に期待すること  部下の変化に気づく 部下の変化に気づく  関心・声かけ・聴く・つなぐ 関心・声かけ・聴く・つなぐ  行動の背景を想像しよう 行動の背景を想像しよう  行動の動機づけは本人に任せよう 行動の動機づけは本人に任せよう  あなたの職場は大丈夫? あなたの職場は大丈夫?  明るく活気ある職場づくり 明るく活気ある職場づくり  メンタルヘルス不調者への対応 メンタルヘルス不調者への対応  うつ病の部下との対応上の注意点 うつ病の部下との対応上の注意点  うつ病の予防策 うつ病の予防策  上司自身の健康と職場への影響 上司自身の健康と職場への影響 |
 |
 |
| SOSに気づくのは誰? |
 |
|
 |
労働者のこころの健康には、作業環境や作業方法などの職場環境、労働時間、仕事の量と質、職場の人間関係などが大きな影響を及ぼします。
これらを適正な状態に保ち、働きやすい環境をつくるために、また個人のこころの健康問題が生じた時に、上司や同僚は、
- 日常接する機会が多く、お互いの状況をよく知っている
- 相互に目が届くため、少しの変化でも気づくことができ、必要な指導・支援がしやすいなどの理由で、 大きな役割が期待されます。
メンタルヘルス研究会が実施した「精神衛生に関する意識と現状についてのアンケート調査」によると、「あなたの事業所で職場内の悩みや問題を持っている従業員に気づくのはどの人か」という質問に対する解答は表に示すとおりです。最も多いのが同僚39.1%、次いで上司26.8%であり、あとに人事担当、家族、部下などの順です。寝食を共にしている家族や、健康管理を担当する専門職種を答えた人は比較的少ないといえます。
日常業務を通じての同僚との接触、上司との関わり合いが、こころの健康に大きな影響力を持つことを示しています。
これらのほかにも、こころの健康の維持・増進、休職後の職場復帰の際の支援など、メンタルヘルスケアの各ステージにおいて、上司や同僚が重要な役割を担うことを示す事例、報告は数多くあります。
| 表.悩みを持っている人に気づくのは誰 |
| 同僚 |
39.1 |
看護師 |
2.9 |
上司 |
26.8 |
カウンセラー |
2.2 |
人事担当 |
10.9 |
保健師 |
0.7 |
家族 |
10.9 |
医師 |
0.0 |
部下 |
5.1 |
その他 |
1.4 |
|
|
 |
|
* i n f o r m a t i
o n ! |
|
i n f o r m a t i
o n ! * |
|
|